NEWS .お知らせ
2025.07.26
BLOG
平田エッセイvol.11:怠惰を求めて勤勉になろう!(後編)
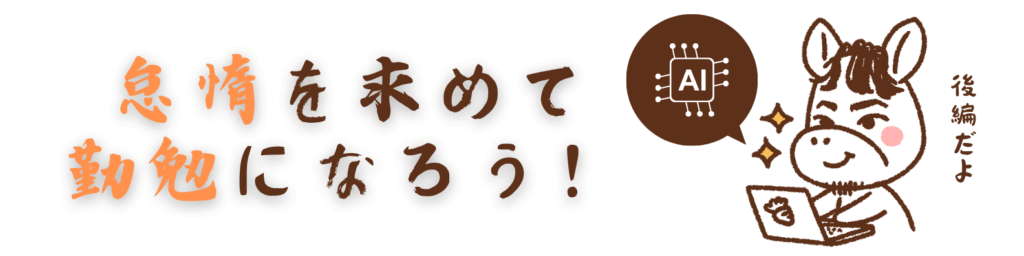
みなさま、お疲れ様です。
気がつけばもう第11話。
1ヶ月に1本のペースで書いていたこともあり、
10ヶ月前の自分は何を考えていたんだろうと過去のエッセイを読み返していたら、なんとびっくり。
10ヶ月前の私も、今の私とまったく同じことを考えていたじゃありませんか。
本当に共感するところしかなくて、自社サイトをブックマークしそうになりました。
やはり18歳で成長って止まるんですね、10ヶ月前と考え方が何も変わっていませんでした。
全然関係ない話ですが、当社補助金事業部の広告物を、
ふじの湯の男湯の脱衣場の衣類等をしまうロッカーに掲出してもらいました。
岐阜にいらっしゃる方で、ふじの湯に行かれる方はぜひご覧ください。
僕はこちらの広告をとても気に入ってまして、
多分だめなんでしょうけど脱衣場で何度も写真を撮ろうと試みましたが、
男性の裸が映り込むと何か色々と厄介な気がしましたので、勇気のある方はぜひご協力をお願いいたします。
さて前回、第10話では「うちの会社でAIをどう活用しているか?」というテーマで、
経営視点での取り組みをまとめました。
今回はその続編。
うちの会社は広告業務と補助金事業の2軸の会社なのですが、現場寄りの実務や管理業務で、
・実際にどんなふうにAIが使われているか?
・今後使っていきたいか?
という話をしていきたいと思います。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
■1. 公募要領や仕様書の要約
補助金や行政の委託事業の仕様書、公募要領って、異常に長いですよね。
あれはきっと、まず「読めるかどうか」で業者をふるいにかけにきてますよね。
これは、PDFをダウンロードしてAIに読み込ませて、ざっくりこう聞きます。
「この資料の概要を300字でまとめて。重要な条件と、注意点もピックアップして」
これで、大体の書類は“18歳以上で成長が止まった大人でも読めるボリューム”になります。
この方法で今までミスったことがないので、お偉いさん方も、多分本来であれば300文字程度の内容を、
格好がつかないので、あえて2万文字にしてるんだろうなと思います。
■2. 社内資料の作成補助
社内向けの資料って、誰かに見せるほどじゃないけど、
「体裁が整っていないと読みづらい」という絶妙なゾーンにあります。
申請資料のフォーマット、年度ごとの方針資料、就業規則に載っていない社内ルールや基準など。
この辺りは、AIに「こういう資料を作りたい」と伝えて、叩き台を作ってもらうと便利です。
“ゼロから書く”という心理的ハードルが消えるだけで全然違います。
また社員全員向けのアナウンスや、顧客向けメルマガなどにも使えます。
ただどちらかというと、心がこもってない文章になることが多いので、
あえての誤字を入れつつ“こいつおっちょこちょいで可愛げあるな感”を出していきましょう。
社内資料なのでこういう小細工をしつつ、私がんばりました!感を出していきましょう。
■3. 行政プロポーザルの事前審査
最近では、自治体や官公庁のプロポーザルに参加する機会も少しずつ増えてきました。
でもあの資料、分量も多いし、“自分たちの提案がズレてないか”を見極めるのが難しい。
……全然話違いますが、長机の端に座っている審査員って、なぜあんなに厳しいんでしょうか。
真ん中の人がズバズバ言ってくることってあんまりイメージないんですけど。
さてプロポーザルって、公募要領を読み込んで、企画書の構成を考えて、レイアウトして、印刷して、準備して…と、
採択されなければすべてが無駄に思えるほど時間と労力がかかります。
1%でも確率を上げたい。
そのためにネゴや営業活動も必要かもしれませんが、まず企画書の“ズレ”を無くすことが肝心です。
そこで、仕様書や公募要領、相手の要件をAIにインプットしてから、こう聞きます。
「この内容で応募する予定だけど、審査員として点数つけて。また、行政側の意図とズレてる点があれば指摘して」
すると、“端に座ってる審査員”並みにシビアに指摘してくれます。
本番前に仮想左端の人を想定しておくことで、
提出後の“お祈りメール”を減らすことができるかもしれません。
■4. ルーティンワークの効率化
「毎月決まったタイミングで、決まった事務作業がある」
こういう仕事、どこの会社にもありますよね。
例えば:
・顧客リストの集計と整理
・領収書の整理・出納帳入力
・経費の仕分け・売上管理
・ルーティンとなった案件対応 など
こうした業務は、フォーマットと流れさえ確立すれば、AIやマクロで自動化できるはずです。(うちも今からです)
特にGoogleスプレッドシートでの関数 × Gemini 活用は、習得すると非常に強力だと思います。
「人間がやるべき作業」がだんだん減っていく感覚は、まさに“支配されている”感じで素敵です。
■5. 社内資料検索の簡易化
「あれ、去年の提案書どこにあったっけ…?」
「旅費規定の最新版、誰が持ってるの…?」
うちの仕事では、“完了した案件の資料を後追いで探す”機会が意外と多いんです。
ウォーキングデッドの世界です。
ハードディスクを探し、フォルダを漁り……
一苦労です。
この“社内迷子”を防ぐために、
NotebookLMやGeminiを活用し、社内資料を一括検索・参照できる仕組みを試験運用中です。
理想は、
・「この件に関する社内ルールと、最近の提案事例を出して」
・「類似案件の企画書と見積もりを出して」
・「あのときの写真データをまとめて出して」
と聞けば、AIが全部拾って返してくれる状態。
これは、組織にとって本当に大きな財産です。早く整備したいです。
■6. 分析業務の初期支援
最後に「分析」もAIの得意分野です。
第10話でも書きましたが、だって東大理Ⅲですから。
例えば:
・アンケート自由記述の分類・傾向分析
・売上データの変動理由のコメント出し
・競合との比較ポイントの要約 など
人間の“なんとなく”を補正してくれるので、提案資料や方針策定の説得力が上がります。
むしろ分析なんてものはそもそもデータを読み解く作業なのですから、人間がやるべきものではないのです。
特に数字をもとに何かを語るとき、
「平田がこう言ってた」と「AIがこう算出した」っていうのはどちらを信じますか、って話です。
まあ、ここはそりゃあもちろんどっこいどっこいでしょうけど(照)
分析はAI、考察と判断は人間。
この組み合わせで進めるのが良いかなあと思っています。
この組み合わせがベストです。
■今後の方針:Googleツールで統一し、AIに委ねる会社へ
SOUでは今後、以下の方針を明確にしました。
「Google機能で統一して、一貫性を持たせる」
・Gmail
・スケジュール
・Googleスプレッドシート
・Meet
・Drive
・Gemini
・NotebookLM
・Chat(チャットツール)
この“Google経済圏”を社内標準にしていくことで、活用の土台を揃える=支配される準備が整うわけです。
まずは私がこの半年でチャレンジしてみます。
また進捗はこのエッセイで共有していきますので、みなさんもぜひ“怠惰に”試してみてください。
■乗り越えるべき“ウォールマリア”
とはいえ、新しい仕組みを入れるというのは簡単ではありません。
「今までのやり方を変える」には、「人の意識を変える」必要がある。
これが一番大変です。
特にスタッフ側の視点では、こう思うのが自然です:
・「AIで仕事が効率化したら、結局また別の仕事が降ってくるだけでしょ?」
・「今までのやり方でようやく慣れてきたのに」
・「考えることはやりたくない、単純作業しかしたくない」
要するに、業務効率化を求めているのは経営層なんです。
スタッフからすれば“頑張っても得しない”ように見えてしまう。
ここが導入最大の壁=ウォールマリアです。
■結論:報酬設計を先に。全社で“得する仕組み”を。
だから、僕はこう考えています。
AIによる業務効率化の“経営メリット”を、
スタッフにも可視的に還元する仕組みが必要だと。
たとえば:
・賃金UP
・成果連動の賞与設計
・自由時間の増加 など
「AIで楽になった分、ちゃんと得をする」
そう見えれば、誰しも前向きに動き出すはずです。
全社が前向きでなければ、AI導入は意味がない。
“効率化したけど、売上も時間も変わらない”では誰も幸せになれません。
ツールの導入より先に、制度の設計を。
これがSOUの第7期で行ってきたことであり、
それを土台に「業務効率化に本気で取り組もう」というのが第8期の挑戦なのです。
そのために、僕は勤勉に頑張ります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ということで、2回にわたる“怠惰を求めて勤勉になろう”シリーズ、いかがでしたでしょうか。
次回のテーマは……
うーん、まだ未定です。
そろそろ「人間にしかできない仕事ってなんだっけ?」みたいな話も書いてみたい気もしています。
なにか書いてほしいテーマがあれば、ぜひ教えてください。
それではまた、次回のエッセイでお会いしましょう。
この時代、怠惰こそが進化の母です。
お楽しみに!
